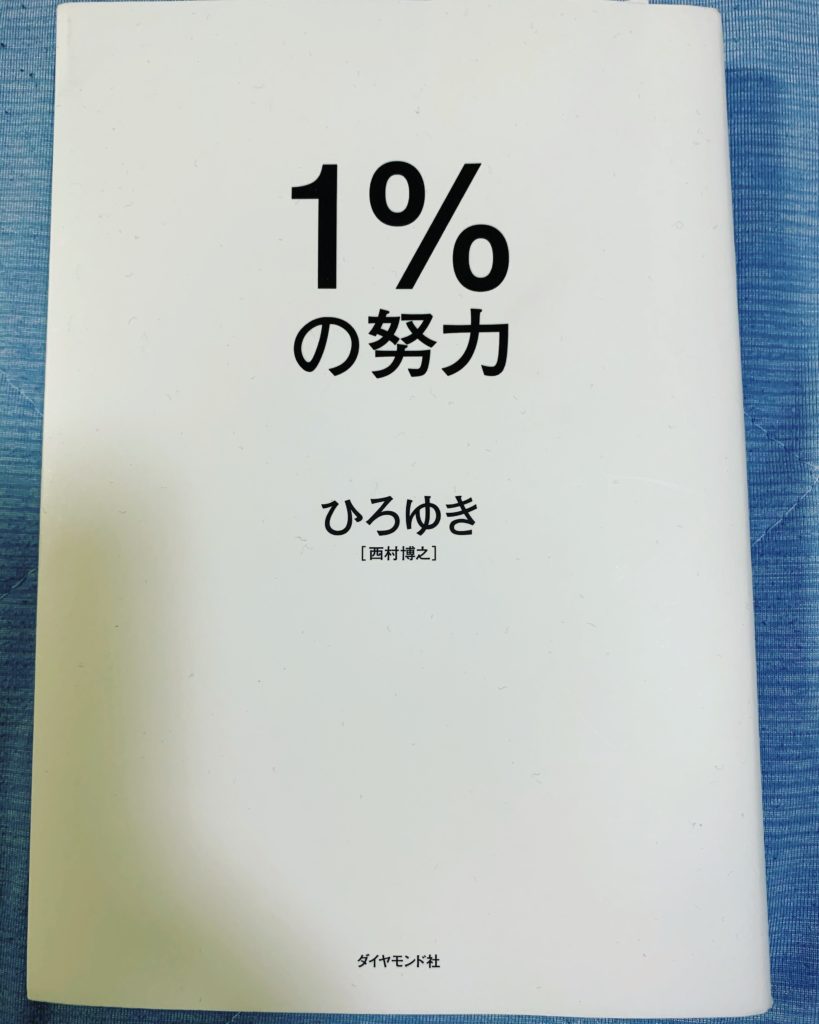
中高生を含む若い世代から、固定観念に縛られがちのおじさん世代まで読んで欲しい本
本はたくさん買う方で全部読む本、途中で読まなくなって、また数年後読み直す本、色々あります。せっかくだから自分のためにもメモを残しておこうかな、と思いました。
この本の筆者は2チャンネルを作った西村博之さんの本。序盤、彼の幼少期の赤羽での団地の経験から最後の結びまで一気に読める面白さがある本でした。
ようは捉え方、考え方をちょっと変えるだけで、楽になれる。生活する手段はいわゆる「正しい方法」とか「学校や社会で一般的に教えられていること、信じられていることだけではない」ということをこの本は一貫して教えてくれているように自分は感じました。
これから進路や人生を考えていく学生の人も、部下を抱えて悩んでいる管理職の人も、いろんな人に「自分の価値観を見つめ直すきっかけ」をくれる本かな、と思いました。
いろんな形の成功があって、いろんな生き方がある。失敗したら「笑い話」にすればいい。笑い話をたくさん持っていることほど誇れることだ。。。最後はそんなポジティブなメッセージで終わっていて、本当に面白い人だと思いました。
メモ(今の自分が気になったこと、考えたことのメモ、抜粋)
・わかりあえない人と出会った場合は「前提が違うのではないか」と疑ってみる。
→人は生まれ育った環境によって考え方が違う。無理に合わせない、合わさせない。
・劣等感を持つ前に周りをよくみる。よく知る。
→自分が信じ込んでいることも案外違うこともある。「危険な地域」は本当に「危険」なのか?「取り返しのつかない失敗」は本当にあるのか、となど、とことん調べてみる。考えてみる。
・壺の話=優先順位の話
→壺をいっぱいにする。岩と砂利と砂と水を入れる。思ったよりもたくさん入る隙間がある。でも順番が大事。「自分にとっての”岩”」を明確に持つこと。
・トップを知る。以外に大したことがない。
→上を知れば、案外そこまでしっかりしていないことも多い。
・仕事の選び方
→好きなことを仕事にするのはそれはそれでしんどい。やりたいことを一段階掘り下げる、「体験」までに落とし込むと見え方が違ってくる。
例)「音楽がやりたい」→「大勢が一体になるライブ感を作りたい」
「ゲームを作りたい」→「何も考えずに没頭できる仕組みを生み出したい」
・成功の要因をしっかり掴んでおく。
→なぜそれが「売れたか?」をしっかり抑えておく。何が成功の根幹にある体験なのか、理解しておく。
・自分の役割を知る。強みを知る。
→自分の仕事の役割を知っておく。軸をしっかり持つ。サブスキルの重要性。サブスキルがあれば潰しがきく。
・しっかりとした戦略・ビジョンがあれば下がテキトーでもうまくいく。
→物事の失敗は判断する上の人たちの判断間違いの方が原因としては大きい。
・努力しても好きでやっている人には勝てない。
→夢中になれる人はやらされている人よりもどんな時も強い。
・人のタイプ
→色々な人がいる。それぞれのタイプに長所がある。できないことを押し付けない。うまく力を引き出す。いろんなタイプの人間が組織には必要。
・社会の評価
→社会ではある特定のタイプが好まれたり賞賛されたりする傾向がある。
・マネージメントの仕方
→①道徳(考え方、哲学)、②法律(ルール)、③市場(やりづらくする)、④アーチテクチャー(仕組みづくり)相手を変えなくてもできる。
・下積みの重要性
→「今、実績を持っているか」を自分に問いかける。うまく行かない時は相手のことをよく考える。あとで楽になってくる。
・あらゆることを調べ尽くす。
→楽したいなら、仕組みを学ぶこと。人と違うことをしたいなら、仕組みを学ぶこと。
・経営者は役者
→嘘を嘘じゃなくする力が必要。
・失敗したらネタにできる。笑い話をたくさん持て
→笑い話をどれだけ持てるかが成功の鍵
是非読んでみてください!
(東頭コーチ談 スタッフ書)